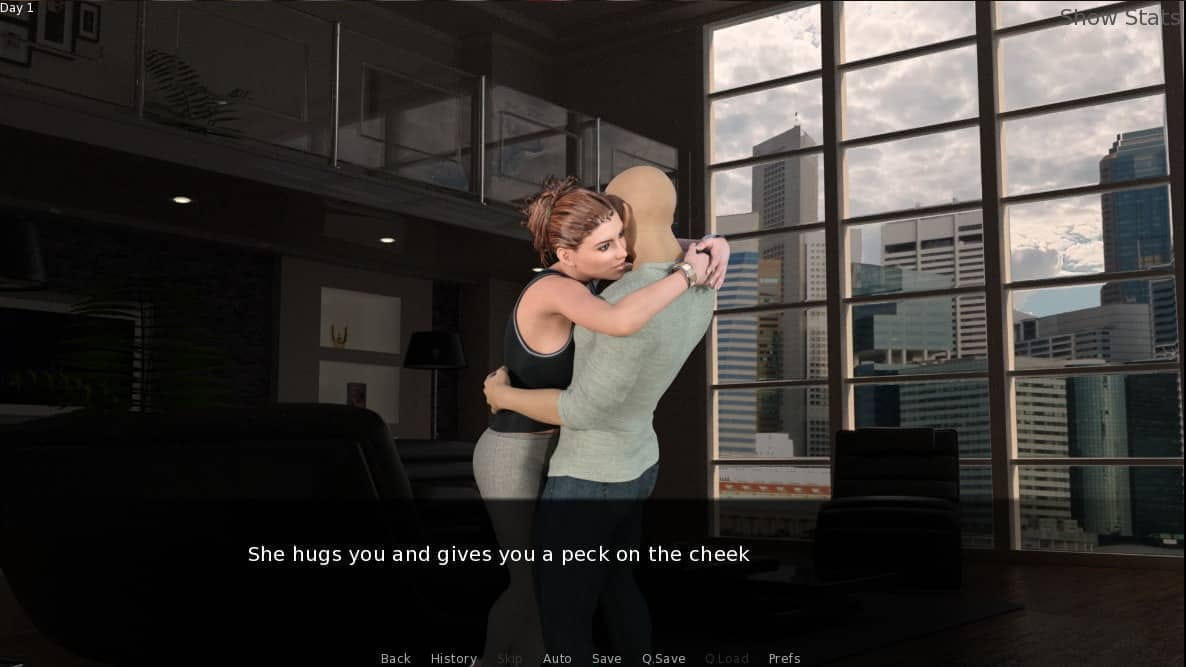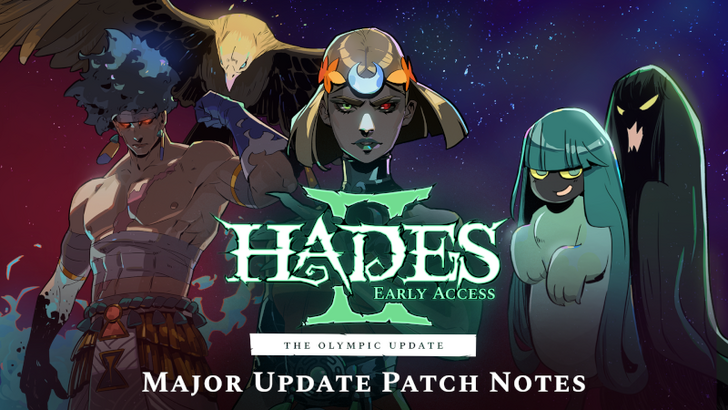元任天堂スタッフが明かすカービィの米国仕様化の秘密

元任天堂スタッフが、カービィの見た目が日本と米国で異なる理由について考察し、欧米市場に向けた任天堂のローカライゼーション戦略に光を当てる。
世界に向けて作られたカービィのよりタフなルックス
欧米のファンを獲得するためのカービィのリデザイン

米国でのカービィのゲームカバーやアートワークでは、より狂暴で決意に満ちた表情が特徴であり、ファンの間で「怒れるカービィ」という愛称で親しまれている。2025年1月16日のPolygonのインタビューで、元任天堂ローカライゼーションディレクターのレスリー・スワンは、欧米の視聴者向けにカービィの外見を変更する選択をした理由を説明した。
スワンは、2000年代初頭に行われたカービィのリデザインは、怒りではなく決意を伝えることを目的としていたと述べた。「日本では、可愛いキャラクターが全年齢にアピールします」と彼女は語った。「しかし米国では、十代の男の子はよりタフな人格を持つキャラクターに引き付けられます」。
2014年のGameSpotのインタビューで、『星のカービィ トリプルデラックス』のディレクター、熊崎神也は、日本が多様なプレイヤーを惹きつける可愛いカービィを好む一方で、米国では「戦いに鍛えられた」カービィにより良い反応を示すと強調した。ただし、『星のカービィ ウルトラスーパーデラックス』のようなタイトルでは、日米双方のパッケージアートでよりタフなカービィが採用され、その真面目な側面と本質的な魅力のバランスが取られており、これが日本における主要な魅力の一つであり続けていると指摘した。
「スーパー・タフ・ピンク・パフ」としてのカービィのマーケティング

任天堂のマーケティングチームは、特に男の子層へのアピールを広げるため、2008年にニンテンドーDSで発売された『星のカービィ ウルトラスーパーデラックス』において、カービィを「スーパー・タフ・ピンク・パフ」としてブランディングした。元任天堂オブアメリカ広報マネージャーのクリスタ・ヤンは、同社が2000年代初頭に「子供向け」というイメージを払拭しようとしていたと説明した。「当時、ゲーム界ではよりクールで成熟した雰囲気を求める流れがありました」と彼女は語った。「『子供向け』というレッテルは大きな弱点だったのです」。
任天堂は、カービィが単なる子供向けと見られないよう距離を置くために、彼の戦闘能力とタフな人格を強調した。2022年の『星のカービィ ディスカバリー』のような最近のプロモーションでは、人格ではなくゲームプレイと能力に焦点が移行している。ヤンは指摘する。「カービィはより多才なキャラクターに形成されてきましたが、大多数のファンにとっては、その可愛さがいまだにタフさを凌いでいます」。
米国におけるカービィのローカライゼーションの変遷

カービィの米国向けローカライゼーションは、1995年の大胆な「Play It Loud」キャンペーン広告で始まった。これはカービィを mugshot(顔写真)のポーズで写したものだった。その後数年にわたり、『カービィのエアライド』(2003年)、『星のカービィ』(2002年、北米タイトルKirby: Nightmare in Dream Land)、『星のカービィ 参上! ドロッチェ団』(2006年、北米タイトルKirby: Squeak Squad)といったゲームでは、米国のパッケージアートで角ばった眉毛と厳しい表情を特徴とするカービィが採用された。
表情以外にも、任天堂は欧米の視聴者にアピールするため、他の調整を行った。1992年、ゲームボーイ用ソフト『星のカービィ』では、米国のパッケージアートに日本で見られたピンク色のカービィではなく、幽霊のように白いカービィが使用された。これは、1993年にファミコンで『星のカービィ 夢の泉の物語』が登場するまで、ゲームボーイのモノクロ表示がカービィの本来の色を隠していたためである。スワンは説明する。「ピンクでふわふわしたキャラクターは、かっこいいと思われたい男の子には響かず、売上の潜在的可能性を損なっていました」。
このため、任天堂オブアメリカはより広範なアピールのために、米国向けパッケージアートでのカービィの表情を調整した。近年、カービィの世界的なマーケティングは統一され、地域を問わず真面目な表情と嬉しそうな表情を使い分けるようになっている。
グローバルマーケティングへの任天堂の転換

スワンとヤンは、任天堂が統一されたグローバル戦略へと移行していることを強調した。任天堂オブアメリカは現在、日本の本社と緊密に連携し、一貫したマーケティングとローカライゼーションを確保している。この転換により、1995年の「Play It Loud」広告のような地域による違いは避けられている。
ヤンは指摘する。「グローバルマーケティングはブランドの一貫性を保証しますが、地域のニュアンスを見落とし、時に過度に安全なキャンペーンにつながることもあります」。また、ゲーム、アニメ、漫画を含む日本のポップカルチャーに対する世界の視聴者の理解が深まったことで、大規模なローカライゼーションの必要性が減少したと付け加えた。
ゲームのローカライザーは、この傾向をゲーム産業のグローバル化と、日本の美的感覚に対する欧米ファンの評価の高まりに起因しており、カービィの世界的な表現におけるより統一されたアプローチを促進していると見ている。